製薬マーケティングのブランディングの基本-顧客からの「信頼」が重要な理由

競争が激化する製薬業界では、製品ライフサイクルの短縮やモダリティの複雑化が進む中、企業や製品の「ブランド価値」をどのように確立するかが重要な課題となっています。科学的エビデンスに裏付けされた医薬品としての機能的価値に加えて、企業活動や製品開発に込められた想いや世界観も伝えていくことが、医療関係者や患者から信頼され、選ばれるためのブランディングには欠かせません。
本記事では、製薬マーケティングのブランディングの基本と戦略の要点を整理し、デジタル時代に求められる新たな展望を解説します。
なぜ製薬業界でブランディングが重要なのか
激化する市場環境における差別化のカギ
製薬業界では近年、市場競争の激化とそれに伴う製品ライフサイクルの加速が課題となっています。
特に生活習慣病などの患者数が多い疾患領域では、類似した薬効の製品が複数上市されたり、新たな治療選択肢が次々と登場したりするため、競合品との差別化が欠かせません。また、モダリティの多様化や複雑化、研究開発・医療行政などの環境変化が進むにつれて、製品のライフサイクルマネジメントは難しくなっています。
そのため、製薬企業はより早期の段階から、市場での製品のポジションを獲得していく必要に迫られています。そのために求められるのが、効果的なブランディングなのです。
ブランディングは、単にイメージや認知度の向上につながるだけではありません。医療用医薬品の選択は命や健康に直結するため、医療関係者や患者から「信頼できる」と思われるためのブランディング戦略は、製品が勝ち残るためのカギとなり得ます。
複雑化するマーケティングでの一貫性の土台
製薬各社のマーケティング手法も、デジタル技術の普及に伴い大きく変化しています。近年は、MR、オウンドメディア、Web講演会などのあらゆるチャネルを組み合わせ、統合した情報提供を行う「オムニチャネル戦略」へと重点が移っています。
オムニチャネルマーケティングでは、各チャネルから医師への情報提供が、一貫した体験として統合されていることが重要になります。その土台となるのが、確立されたブランディング戦略です。
さらに、モノも情報も氾濫する現代において、医師や患者を含む多くの人が、モノそのものよりも「意味のある体験」を重視する傾向があります。いわゆる「イミ消費」志向が強まる中、製薬マーケティングにおいてもブランドの世界観や社会的価値が重要性を増しています。
単に製品名を知ってもらうだけでなく「製品・企業が患者のために何をもたらすのか」というブランディングも加えることで、より深い信頼を得られるでしょう。
製薬業界におけるブランディングの基本
製薬企業のブランディングの特徴
製薬企業のブランディングでは、「科学的エビデンスに裏付けられた機能的価値」と「情緒的価値」の両立が求められます。
医療用医薬品では、有効性や安全性といった機能的価値が特に重視されるため、承認時資料や診療ガイドライン、確立された研究結果などの科学的エビデンスを、いかに効果的に伝えるかが重要になります。一方、患者にとっては「この薬は安心して使える」といった情緒的価値も、使用する上で重要な側面といえるでしょう。そこで、製品にまつわるストーリーや患者への想い、つながりなどを伝えることで、製品や治療へのよい印象を持ってもらうことも、患者の安心感につながると考えられます。
また、同様の観点から、企業ブランディングも重要と考えられます。企業としての信頼性が高ければ、製品に対しても「この製薬企業の薬なら大丈夫だろう」と前向きに受け取られやすいでしょう。したがって、製品ブランド戦略と企業全体のブランド戦略を両輪で考える必要があります。
さらに、ステークホルダー(利害関係者)の多さも製薬企業のブランディングの特徴です。患者やその家族はもちろんのこと、医師、薬剤師などの医療関係者、さらには行政や保険者まで、多様な利害関係者が製品を取り巻いています。そのそれぞれに適切なコミュニケーションを取り、製品への理解と信頼を醸成することが求められます。
製薬マーケターが押さえるべき3つの要素
1.自社や製品を取り巻く環境・顧客を分析する
ブランディング戦略を策定していくためには、まずは自社や製品を取り巻く環境や顧客について、戦略的に分析することが不可欠です。環境分析やターゲティング、顧客理解などに関するフレームワークを用いて、自社や製品の強みはどこにあるのかを探していきましょう。

2.ブランドの「コアメッセージ」を明確化し、ストーリーを仕立てる
前述の分析をもとに、企業や製品が提供する価値の核を言語化しましょう。「企業としてどのような価値を患者に提供できるのか?」「この製品はどのような価値を提供するのか?」。これらをシンプルなコアメッセージで表現します。企業や製品の価値を一言で示せるメッセージがあると、あらゆる施策の軸がぶれません。このコアメッセージをもとに、ブランドストーリーを仕立てていきます。

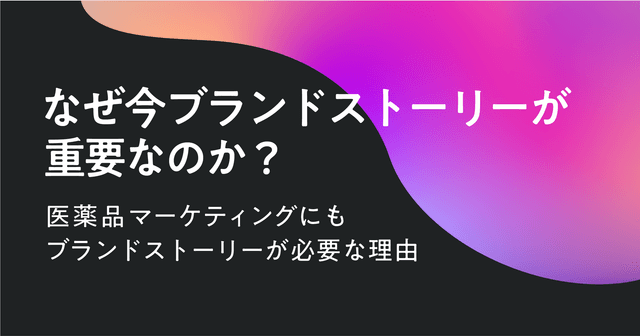
3.一貫したブランド体験を設計する
医療関係者や患者がブランドに触れるあらゆる場面で、統一された体験価値を提供できるよう、ブランドの構成要素を構築していきます。ブランドは、ブランドアイデンティティ、抽象的ブランドメディア、可視的ブランドメディアの3階層で考えることができます。
- ブランドアイデンティティ:顧客(医療関係者や患者)からどのように見られたいかという、ブランド独自のイメージ。
- 抽象的ブランドメディア:ブランドのイメージを表現するキャッチコピー・ロゴ・デザインなどの要素。
- 可視的ブランドメディア:キャッチコピー・ロゴ・デザインなどの抽象的ブランドメディアをもとに作った、パンフレットや広告などの各媒体での表現。
これらの設計を通して、例えばMRの持参する資材、Web講演会の内容やトーン、患者向けサポートプログラムやモバイルアプリの使い勝手に至るまで、全てにおいてブランドのメッセージや世界観が一貫していることが理想です。
製品そのものだけでなく、患者に支援を届けたい想いなどまで包括的に設計することで、機能的価値を上回る情緒的価値をも提供し、消費に意味をもたせることができます。
例えば、ある製品のコアメッセージが「患者の生活の質(QOL)の向上」なのであれば、疾患啓発サイトや患者サポートアプリの提供などを通じて一貫したメッセージを送り、QOL向上のヒントを提供するといったように、ブランドイメージをあらゆるタッチポイントで体現していくことが必要です。
デジタル時代の製薬ブランディング戦略
デジタル技術がますます発展し、多様な手法が出てくる中で、製薬企業のブランディングでもデジタルチャネル活用は欠かせない要素となっています。
オウンドメディア・SNSの活用
一般向けの疾患啓発サイト、患者向けの製品サイト、医療関係者向けサイトなどの自社オウンドメディアや、SNS、広告などで情報提供を行いましょう。オンライン上でブランド認知や親近感・信頼感を育むためには、SEO戦略とコンテンツマーケティングが重要になります。


サードパーティーメディアの活用
医師向けプラットフォームであるm3.comやCareNet.com、日経メディカル、メディカルトリビューン、MedPeer、HOKUTOなどを通じた医師への情報提供も有効です。例えば、m3.comは33万人以上の医師が登録1)する国内最大の医師向けメディアであり、製薬企業向けのサービス(MR君など)を利用して効率的にターゲット医師へアプローチできます。これらの専門プラットフォームを通じて情報提供を続ければ、忙しい医師にもリーチしやすく、自社製品や企業への好意度を高める効果が期待できます。
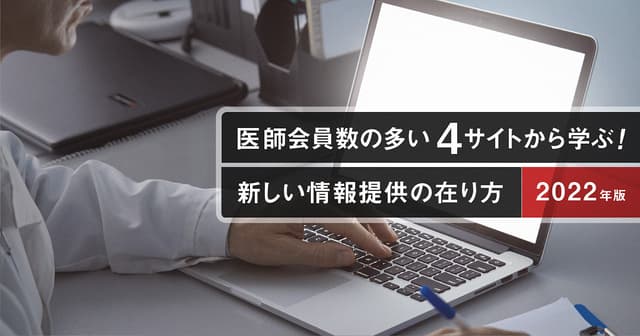
Web講演会の活用
医療関係者向けのWeb講演会(ウェビナー)は、コロナ禍を経て、製薬企業にとって最もスタンダードな施策の1つになりました。最新エビデンスの紹介や疾患治療ガイドラインの解説など、専門性の高い情報提供をオンラインで行うことで、医療関係者へのブランドイメージ向上とプロモーションを図ることができます。リアル講演会に比べると地理的な制約がなく、多くの医師にリーチできる点でも有用です。


MRからの情報提供
MRは、製薬企業のブランディングとプロモーションにおいて最も重要なチャネルの1つであり、医師の処方意向への影響力は依然として相対的に強いと考えられています。
デジタルシフトや医師の働き方改革の影響などもあり、MRから医師への情報提供(ディテーリング)の機会が減ったと言われて久しくなります。しかし、Web講演会後のMRによるフォローの有効性が指摘されている2)ほか、最近では製薬本社において「MR回帰」の意向が聞こえることもあります。
MRに製品のブランディング戦略を知っておいてもらうこと、MRが使用する資材に一貫したブランドイメージを適用することは、オムニチャネルでのブランディングのために欠かせないといえるでしょう。
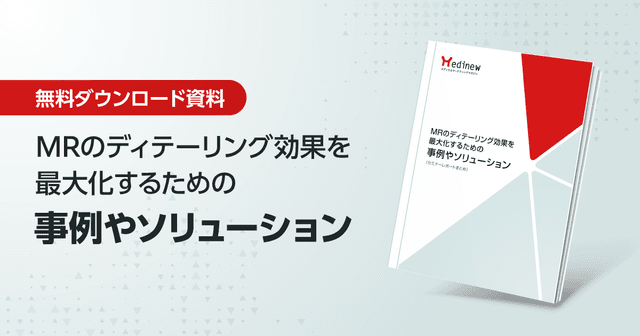
DTCマーケティングの可能性
DTC(Direct to Consumer)マーケティングとは、一般生活者に直接訴求するマーケティングです。日本では、法規制上、一般生活者向けの医療用医薬品の広告が認められていません。そのため、製薬企業のDTCマーケティングは、疾患啓発や企業ブランディングといった形で行われることになります。
一般向けの疾患啓発では、製品名を出せないなどの制約はありますが、疾患に関する正しい知識を広めることができます。潜在的な患者が症状に気づき、受診して診断を受けることになれば、間接的に治療の普及に貢献します。
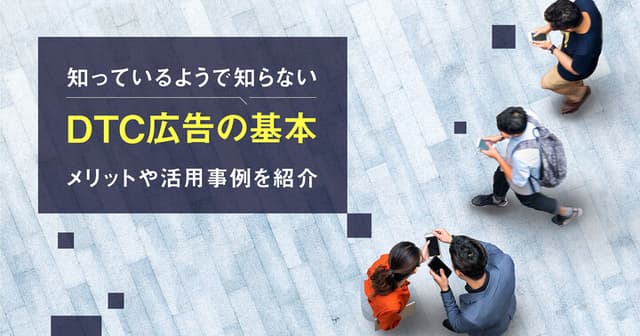
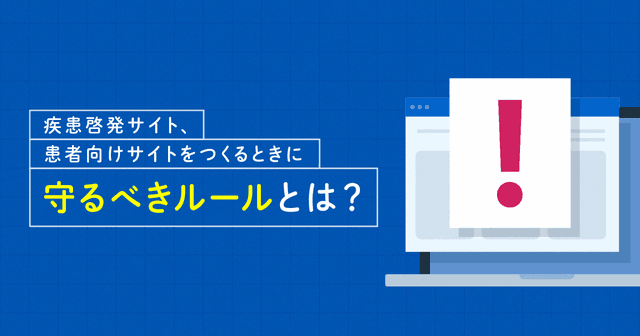
製薬企業のブランディングのこれから
製薬企業のブランディングのアプローチは、今後も技術革新や医療環境の変化に伴って進化していくと考えられます。そのトレンドの一部を紹介します。
AIによるパーソナライズドマーケティング
人工知能(AI)やビッグデータ・リアルワールドデータの活用により、ターゲットごとに最適化した情報提供が可能になってきます。医師一人ひとりの処方傾向や関心領域に合わせてコンテンツを出し分けたり、患者一人ひとりの属性・選好に合った情報提供を行ったりする「ハイパーパーソナライゼーション」が今後は進むでしょう。こうしたパーソナライズ施策は、情報過多の時代において顧客体験を向上し、ブランドへの信頼を高めるために役立ちます。

オムニチャネル戦略の深化とHaaS
今後は、デジタルチャネルとMR・MSLがより高度に連携し、オムニチャネルでの情報提供を行うことが求められます。チャネルを超えて一貫性のあるコミュニケーションを実現することで、医療関係者への情報提供の質とスピードが向上し、製薬企業との信頼関係の強化につながります。
また、ヘルスケアをサービスとして提供する概念である「HaaS(Healthcare as a Service)」は、製品そのものに加え、健康管理アプリや疾患管理アプリ、遠隔医療支援サービスまで含めてソリューション提供するモデルです。製薬企業がHaaSを取り入れれば、患者理解を深め、治療体験全体を支援し、ブランドへのロイヤルティを高める新たな機会が生まれるでしょう。

メタバース・VRを使った新たな体験
仮想空間(メタバース)やVR(仮想現実)の技術も注目されています。例えば、アステラス製薬は2022年、メタバース上で医療関係者向け講演会を試験開催しています3)。仮想空間にMRや医師のアバターが集い、現実さながらにディスカッションできる環境を整える試みです。このような場所の制約を超えた情報提供や、仮想空間上で薬の作用機序を3Dで見るといったバーチャルプロダクト体験などは、今後ますます進化する可能性があります。
VRを用いた研修・教育プログラムや、患者向けのリハビリ支援VRコンテンツなども、ブランド価値を高める新しいアプローチとして期待されます。
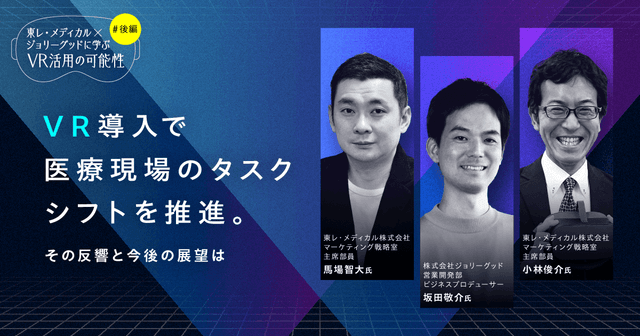

データドリブン×感情マーケティング
テクノロジーが発達しても、最後に人の心を動かすのは「想い」や「共感」です。蓄積したデータを分析して的確なターゲティングや効果測定を行う一方、発信するメッセージは人間味を感じられるものであることが大切です。
データに裏打ちされた理論と、人の心に響くクリエイティブの融合が、これからのブランディング成功のカギを握ります。数字と感性の両面からブランドを育てるアプローチを意識しましょう。
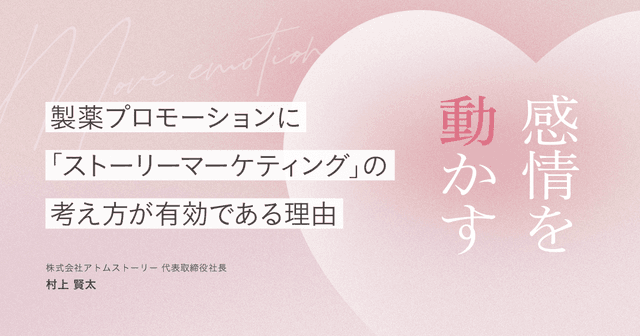
まとめ:製薬マーケターが今すぐ取り組むべきこと
この記事では、製薬業界のブランディングの基本と戦略について解説してきました。
ブランディング戦略は、製品単体の認知向上のみならず、企業・疾患領域全体の価値向上に直結しています。 科学的エビデンスに裏打ちされた誠実な情報提供や、患者の心に寄り添うサービスを通じて、着実に医療関係者・患者との信頼を積み重ねていくことが大切です。
これからの製薬マーケティングでは、デジタル技術のさらなる発展により、ますます複雑になっていくオムニチャネルの精度を高め、一貫したブランド体験を提供していくことが重要です。 リアルとWebにまたがる多数のタッチポイントにおいて、ブレないメッセージを届けることにより、ソリッドなブランドイメージを確立することができます。
マーケターがまず取り組むべきなのは、「コアメッセージの明確化」と「タッチポイントの強化」です。地道な取り組みの積み重ねが、やがて企業や製品の確固としたブランドの確立につながります。医療関係者や患者から選ばれる存在になるために、戦略的なブランディングに取り組んでいきましょう。
〈参考文献〉
1)m3.com CAREER
https://career.m3.com/admin/(2025年3月24日閲覧)
2)医師の製薬企業主催講演会の活用実態とニーズ調査 2024【DL資料】
https://www.medinew.jp/downloads/research/seminar_drsurvey2024
3)アステラス製薬のデジタルトランスフォーメーション2022年1月21日 メディア説明会
https://www.astellas.com/en/system/files/media_briefing_jp_20220121-00.pdf
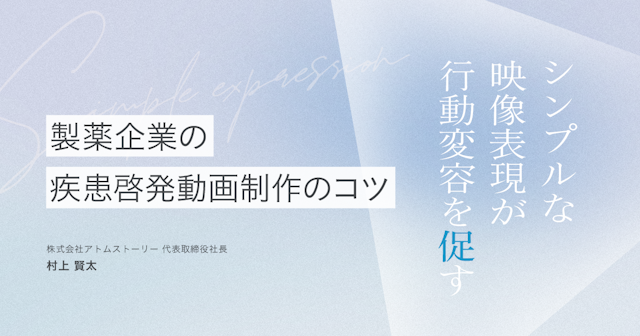
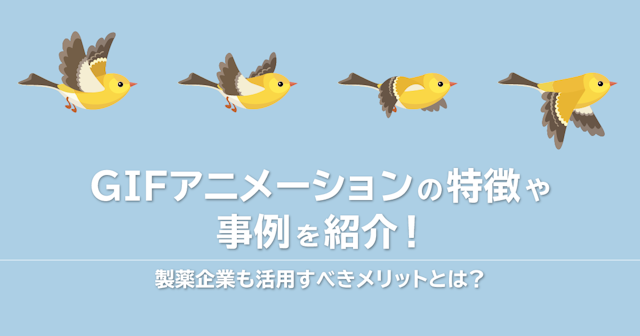

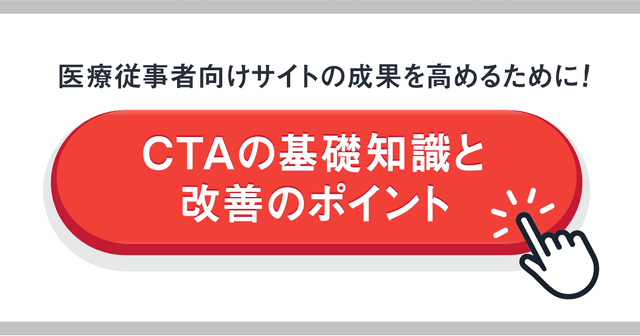







.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



