【2025年最新】疾患啓発サイト、患者向けサイトをつくるときに守るべきルールとは?

医療用医薬品に関するWebサイトの制作・運営では、法規制やガイドラインに基づいた適切な情報提供が求められます。特に、医療関係者向けの情報提供では、法規制やガイドラインを厳格に守らなければならないことはよく知られており、それらを念頭に置いて制作・運営が行われていることが多いです。
一方、医療関係者以外を対象とした情報提供ではどうでしょうか。近年、一般の人を対象とした「疾患啓発サイト」や、医療用医薬品を使用している患者さんを対象とした「患者向けサイト」を制作・運営する製薬企業が多くなっています。これらのサイトはそれぞれ異なる目的のためにつくられますが、医療関係者向けサイトと同様、守るべきルールをきちんと把握し、慎重に対応する必要があることは同じです。
Webサイトを通じた情報提供の重要性が増す一方で、不適切に運用すると大きな問題に発展する可能性もあります。
本記事では、製薬企業の実務担当者が知っておくべき、一般人向け・患者向けサイトでのコンテンツ表現に関するルールと適切な対応方法について解説します。
一般人・患者家族向けの疾患・医薬品情報では「広告の3要件」に注意
日本では、一般の方に医療用医薬品の広告を行うことは、薬機法および医薬品等適正広告基準(以下、適正広告基準)で禁じられています。
医薬品等適正広告基準 第4の5(1)
医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。
このような規制がありますから、疾患啓発サイトや患者向けサイトには、医療用医薬品の広告を掲載することはできません。
ルールを守って適切な情報提供を行っていくためには、「広告」とは何かを知り、「広告」に該当しない情報提供について理解しておく必要があります。
医薬品などの広告の定義については、厚生省医薬安全局監視指導課長通知(平成10年9月29日付 医薬監第148号)で、いわゆる「広告の3要件」として示されています。以下の全てに該当する場合、「広告」と判断されます。
広告の3要件
- 客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること(取引誘引性)
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
裏を返せば、これら全てを満たさなければ広告に該当しないということになります。そのため、疾患啓発情報や、特定の疾患の患者・家族に向けた医薬品関連情報は、それぞれ単独でみると原則として広告には該当しません。しかし、表現の仕方や組み合わせによっては広告の性質も持ちうるという、広告との境界が極めてあいまいな位置に存在しているとも言えます。
従って、疾患啓発サイトや患者向けサイトで情報提供を行う際は、まずこの「広告の3要件」に該当しないよう注意する必要があります。コンテンツ制作時の具体的な留意点は後半で紹介します。
疾患啓発サイト、患者向けサイトの特徴と役割
「疾患啓発サイト」と「患者向けサイト」は、どちらも何らかの疾患に関する情報を提供しており、医療関係者以外を対象としているという点は同じです。しかし、その目的は少し異なります。
各サイトの特徴
項目 | 疾患啓発サイト | 患者向けサイト |
|---|---|---|
目的 | 特定の疾患に関する正しい知識の提供し、早期受診や予防の重要性を啓発する | 医薬品の適正使用を支援する |
対象 | 一般生活者 | 医療用医薬品を実際に使用している、またはこれから使用する患者 |
提供情報 |
|
|
医薬品の推奨 | 特定の医薬品や治療法を推奨することはできない | 承認された内容に基づく医薬品情報を提供 |
姿勢 | 疾患に関する一般的な情報提供に徹する | 医薬品の正しい使用方法や安全性に重点を置く |
目的 | プロモーション色がある (患者獲得を少なからず想定) | プロモーション色は原則なし |
ケース・バイ・ケースにはなりますが、「疾患啓発サイト」は医療用医薬品プロモーションの枠組みの中で制作されるという性格を持っています。自社医薬品を推奨するようなあからさまな表現は、広告となってしまうので禁止されていますが、しかし単なる疾患情報の提供のみにとどまらず、患者掘り起こしなどを介しての患者獲得も少なからず想定していると考えられます。
それに対し、「患者向けサイト」はすでに自社医薬品を使用しているか、これから開始する患者を対象としています。適正使用や安全対策の情報に限定して提供するため、原則としてプロモーションは主目的ではありません。
このように2つのサイトは目的が異なるので、医師や医療関係者が対象ではないという点では共通していますが、コンテンツの表現方法や留意事項は異なるのです。
疾患啓発サイト、患者向けサイトで守るべき表現のルール
日本製薬工業協会(製薬協)では、会員会社がホームページにコンテンツを掲載する際の自主規範として「ホームページへのコンテンツ掲載に関する指針」を作成しています(平成28年7月15日付製薬協発第497号、令和4年8月24日改定)。
この指針では、一般人向けの情報提供を、1)製品や疾患に関心のある一般人を対象としたコンテンツ、2)製品を服用する患者とその家族を対象としたコンテンツ*に分け、それぞれ次のような点に留意するよう喚起しています。
*1)は「疾患啓発サイト」、2)は「患者向けサイト」に相当
ホームページへのコンテンツ掲載に関する指針より(一部抜粋・要約)
1 製品や疾患に関心のある一般人を対象としたコンテンツ(疾患啓発サイト) |
|---|
|
2 製品を服用する患者とその家族を対象としたコンテンツ(患者向けサイト) |
|---|
|
参考:日本製薬工業協会. 医療用医薬品製品情報概要等作成上の留意点 2024年4月.P282-5.
言うまでもなく、薬機法や適正広告基準を遵守することは前提とした上で、これらのルールを守る必要があります。
以上のほか、「医療用医薬品の販売情報活動提供に関するガイドライン」では、疾患啓発の情報提供に当たっては、医療用医薬品による治療のみを推奨して、医療用医薬品以外の治療手段がないかのように誤認させるような表現を禁じています。
コンテンツ制作で気をつけたい、好ましくない表現例
医療用医薬品関連の疾患啓発サイトや患者向けサイトでは、過度の期待や不安を引き起こす可能性のある極端な表現は好ましくありません。一般の人や患者さんの誤解を招かないよう、十分気をつける必要があります。ここでは好ましくない表現の例を紹介していきます。
「〇〇症状がある場合、この病気の可能性が高いです」
症状の記述が限定的で、病気を断定するかのような表現になっています。病気の診断は検査などを含めて医師が行うものなので、何らかの症状があるからといって特定の病気である印象を与えるような表現は好ましくありません。必要に応じて、医師などへの相談を促す内容を盛り込むことも検討します。
「○○疾患はくすりで治せるようになりました」
疾患に対する対処法を記載する場合は、薬物治療だけでなく、想定できる対処法(安静、運動療法、栄養療法、外科的治療など)を公平に記載する必要があります。
「このまま放置すると、重篤な病気に進行する恐れがあります」
疾患のリスクを説明する場合は、医学的に正しい内容であったとしても、不安をあおることがないよう表現には細心の注意を払うことが必要です。特定の症状や疾患が必ず発現・発症するような誤解を招く表現は好ましくありません。
「適切な治療を行うことで完治が期待できます」
治療について記載する場合は、医療機関で治療を受ければ必ず治るという印象や過度な期待を与えることのないよう、表現に注意することが必要です。また、治療前後の様子を視覚的に示して比較することも、過度な期待につながるので好ましくありません。
デジタルコンテンツ特有の留意点
疾患啓発や患者向け情報提供をWebサイト上で行う場合、外部サイトへのリンクについても慎重な管理が必要です。リンク先のコンテンツが製薬企業サイトのリンク先としてふさわしいかを事前に確認して選定し、内容の適切性も定期的に確認します。外部サイトへ誘導するリンクを設定する場合は、クリックした際にサイトを離れることを明示する仕組みも必要です。
また、現在のデジタルマーケティング環境においては、Cookie規制への対応も求められています。利用者のプライバシーを保護するために、Cookieの利用目的を明確にし、必要に応じて同意を取得するプロセスを導入することが推奨されます。
詳細はMedinewの解説記事を参照ください。
▼関連記事
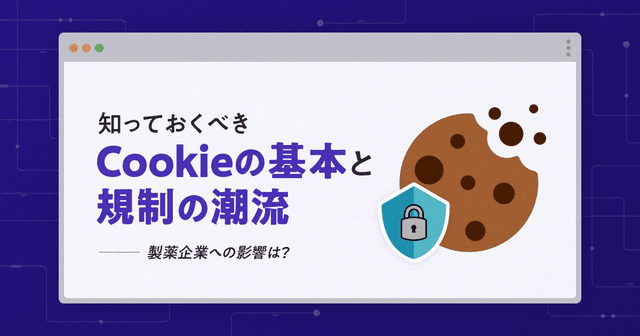
ルールを理解し、適切な表現を用いた情報提供を心がけよう
製薬企業のWebサイト運営においては、法規制やガイドラインを遵守し、利用者に配慮したコンテンツの表現方法が求められます。疾患啓発サイトと患者向けサイトでは、それぞれの目的に応じて、提供する情報の内容は異なりますが、コンテンツの表現方法についての基本的な考え方は変わりません。
表現の良否については、明らかな強調・誇張などは判断しやすいですが、微妙なニュアンスの場合は判断に迷うことがあるかもしれません。そのような場合は曖昧なままにせず、社内審査担当者や外部の有識者に相談して解決を試みましょう。
<出典> ※URL最終閲覧日2025. 1.30
1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
2)医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日付 薬生発0929第4号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf
3)薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日付 医薬監第148号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
4)日本製薬工業協会.ホームページへのコンテンツ掲載に関する指針.医療用医薬品製品情報概要等作成上の留意点 2024年4月.P282-5.
5)医療用医薬品の販売情報活動提供に関するガイドラインについて(平成30年9月25日付 薬生発0925第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000359881.pdf
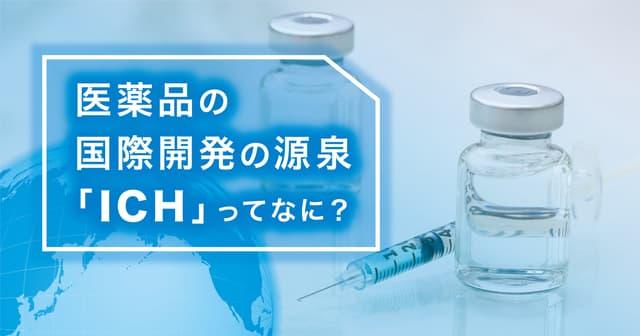


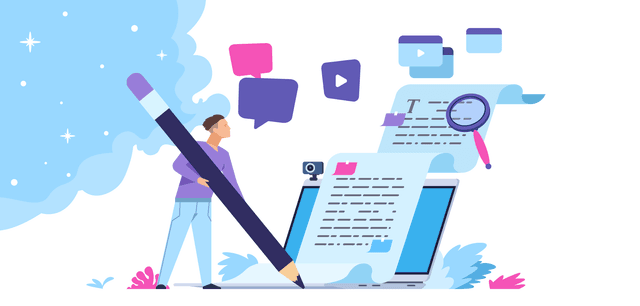







.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



