#3 部門を横断した連携で実現する、製薬企業の地域戦略|地域ビジネスプランニング

医療ニーズの地域差拡大が予想される中、製薬企業には地域ごとに戦略や施策を最適化する「地域ビジネスプランニング」が求められるようになってきました。今回は、地域ビジネスプランニングを実行する際に組織として気を付けるべきポイントを、大手製薬企業3社にてセールストレーニング部門をリードするなど組織マネジメント経験に富むSalesTrainingLabo 代表 干潟 健夫氏と、リアルワールドデータを活用し製薬企業のマーケティング活動をサポートする株式会社JMDC 製薬本部 マーケティングソリューション部 部長 小沢 晴久氏にお聞きしました。
共通認識の醸成と施策の役割分担で、部署・職種間の連携体制を構築
―前回までの取材では、医療ニーズの地域差拡大に伴って地域の実情に合わせた戦略や施策を立案する「地域ビジネスプランニング」が重要になってきていること、詳細な地域分析が可能になったことで地域ビジネスプランニングは実現しやすくなってきていることをお聞きしました。しかし、現時点で地域ビジネスプランニングに取り組んでいる製薬企業は、一部にとどまっています。それはなぜなのでしょうか。
小沢氏:地域ビジネスプランニングを実行するには、本部のマーケティング関連部署と、現場でその施策を実行するMRさんやMSLさんが協力することが大切ですが、その連携の難しさが大きな障壁のひとつとなっていると考えています。
干潟氏:各者の連携が難しい要因の一つに、共働における「Why」、つまり共に働く意義や目的を現場レベルで共有できていないことが挙げられます。現状では、部署・職種ごとに追っている目標が異なるため、それぞれの責任範囲以外には必要以上には関与しないというような傾向も各社にみられるようです。
この課題を解決するには、「企業としてその製品を通じたより良い地域医療のために何を目指すのか」について、各者が共通認識を持つことが大切です。具体的には、「企業や製品のブランド力向上」の他、地域に漏れなく必要な医薬品を届け、患者さんに最適な医療を提供するという製品を通じた「地域医療の最適化」が製薬企業の社会的役割の一つであることを全員が認識し、それが全うできた時の状態が具体的な目標として共有されている状況が望ましいでしょう。このように最終的な目標を共有できていれば、互いに建設的な議論をしやすくなります。
とはいえ、ゴールは共通でも、それを達成するための要件はいくつかあります。だからこそ、どの部署・職種が、どの要件達成にコミットするかという役割分担が大切です。
―各者の役割分担は、どのように行うべきでしょうか。
小沢氏:各者が、自ら果たすべき役割について納得している状態を作る必要があるでしょう。
近年は、医療ビッグデータに基づいて詳細な地域分析ができるようになり、それぞれの地域における診断率や薬物治療率、薬剤処方率などの定量的な情報を得られるようになってきました。この情報に、MRさんが蓄積している定性的な知見を掛け合わせることにより、ペイシェントジャーニー上のどのプロセスにボトルネックがあるかを可視化できます。つまり、どの部署・職種がどのような役割を果たすべきかが見えやすくなり、各者が自分の責任範囲について納得しやすくなっているのです。
例えば、地域分析の結果、同種同効薬の中で自社薬剤の処方率が相対的に低いことが明らかになった場合は、医療関係者の意識を変えることが重要だと考えられるため、MRさんのアクションが求められる可能性が高いでしょう。一方、診断率や薬物治療率が低い場合は、本部のマーケティング関連部署やMSLさんなどが疾患啓発に取り組むことが有効な打ち手になるはずです。
干潟氏:特にMSLさんは、現状では、地域医療というよりも、全社的なMedical戦略に従って、医師とのハイレベルなサイエンティフィックなコミュニケーション活動を行ったり、MRさんからの依頼で、MRさんが対応できない科学的知見に関する医療関係者とのコミュニケーションを担うことが多いようです。しかしながらこれからは、より地域医療への貢献という観点から、医療関係者に対して、科学的な根拠に基づいて、より良い医療のあり方を啓発するといった、より地域医療の現場に近い活動が重要になってくると考えられます。言い換えれば、地域のオピニオンリーダーと共に、地域医療の最適化を目指して、MRさんだけでは対応できない、その地域のPatient Journey全体の最適化のためのより積極的で戦略的なサイエンティフィック・エンゲージメント活動を実践することが期待される職種なのだと考えます。以前に比べて、地域分析データを活用することで各地域の医療課題を可視化しやすくなった今、MSLさんもこのような役割を果たしやすくなっているでしょう。
小沢氏:大切なことは、地域分析のデータは、各者が本来の職務や役割を果たしやすくするために使うべきであるということです。つまり、データは各者にとっての成績表ではなく、武器として捉えるべきだと考えています。
PDCAサイクルでは、各段階の主導者決定と情報共有の仕組みづくりが大切
―地域ビジネスプランニングを実行するにあたり、共通認識の醸成と施策の役割分担という土台ができた後は、どのようにPDCAサイクルを回していくべきでしょうか。
干潟氏:まず「P(Plan:計画)」の段階では、各地域の特性を踏まえ、地域ごとに「どのKPIを重視するか」「どの程度のリソースを投入するか」といった優先順位をつけることが大切です。
具体的には、地域分析のデータを見たときに、競合品とのシェア争いで負けている地域はPatient Flowの下流が課題であるわけで、その地域ビジネスプランはMRさんが力を発揮するPlanであるべきです。一方すでにシェア争いで競合に勝っている地域で、診断率の向上や薬物治療の浸透が課題である地域では、MSLさんのリーダーシップによる地域メディカルエデュケーション活動などが優先的にPlanされることが求められます。つまり、地域分析のデータを見たときに、その地域ごとの課題を明確化して、それぞれの役割を担うものが優先順位を持ったPlanとKPIを持つこと、そしてそれを共有することが求められます。
この段階は、本部のクロスファンクショナルなブランドチームがリーダーシップを発揮して主導するのがよいでしょう。本部が整理しなければ、例えば複数エリアを担当するMSLさんの限られたリソースを営業エリア間で取り合ってしまうなど、現場の混乱を招く可能性があるからです。地域ビジネスプランニングの取り組みが円滑に進むようになるまで、少なくとも数年間は本部が「交通整理」の役割を果たすべきだと考えます。
その後、「D(Do:実行)」の段階では、本部とMRさん、MSLさんの各者が、前段階で立てた計画について納得した上で施策を遂行していくことがポイントとなります。そのためには、意見交換できる仕組みづくりと、互いの責任範囲を決定していく役割分担が必要です。
多くの製薬企業では、本部とその地域を担当するMRさん、MSLさんが定期的に話し合う会議体が設けられていません。その上、たとえ意欲的な社員が個人的に別部署と連携しようとしても、数値などの客観的な裏付けに基づいた提案になっていないせいで、実現に至らないことがほとんどです。
そこで、四半期ごとなどのタイミングで、本部とMRさん、MSLさんが出席する会議体を設け、現状の実績と今後の目標について確認するのが有効な打ち手となり得ます。その上で互いに数値的な根拠を見ながら、各者の責任範囲と果たすべき役割を確認し、合意に至るのが理想です。ここで全員が「どのような背景で、どの部署・職種が、何をするのか」を理解できていれば、施策もスムーズに実行できるはずです。
小沢氏:次の「C(Check:評価)」と「A(Action:改善)」の段階では、施策を実行した後の変化の有無を確認すると共に、その結果の要因を検証する作業が重要となります。そもそも結果のデータ自体は、「なぜその結果になったのか」という理由を説明してはくれないからです。
この検証作業には客観的な目が必要なため、各営業エリアのMRさんやMSLさんを巻き込みつつも、基本的には本部が主導して進めていくのがよいと考えます。
干潟氏:その際、診断率や薬物治療率、薬剤処方率といった大きなKPIは本部が管理すべきですが、各KPIを改善するための具体的な施策実施上の課題解決については、各営業エリアの営業マネージャーがファシリテートすることが理想だというのが私の意見です。
従来、マーケティングや営業活動に関わるデータは本部が管理しており、営業マネージャーは本部が決めた施策を実行するのみというケースがほとんどでした。その対象はPatient Flowの下流、つまり自社製品のシェア拡大にフォーカスがあったのですが、地域ごとの詳細な数値データが得られるようになった今は、営業マネージャー自身が、Patient Flow上流に活動するMSLさんの施策の結果も見ながら要因を分析し、改善策をファシリテートするという、課題発見型、プロジェクト型のアクションが取りやすくなっています。つまり、詳しい地域分析データを可視化できるようになったことで、営業マネージャーには、より地域医療全体を俯瞰して捉え、よりブランド価値を高め、売り上げを効率的に高めるための地域戦略を、主体的に考え、行動してもらうための土台ができたのです。
とはいえ、具体的な改善策の立案と実行を、各営業エリアの営業マネージャーに全て任せてしまうと、エリアごとに施策の差が出てしまいかねないので、本社に強力なサポーターがいることが望ましいでしょう。いずれにせよ、互いに相手に対して「丸投げする」状態だけは避けるべきです。
製薬企業と医療関係者が、地域医療の同志として協力し合う未来を目指して
―地域医療の最適化を実現するために、今後製薬企業はどのような姿勢で地域ビジネスプランニングを進めていくべきでしょうか。
干潟氏:これまで、製薬企業と医療関係者は、医薬品を提供する側と使用する側という、対極の存在でした。しかし、今後は地域医療における「同志」になれるはずです。地域医療の実態が数値で詳しく見えるようになることで、そのデータをもとに地域医療の抱える課題や、今後の打ち手について議論できるようになるからです。地域医療の最適化に向けて、製薬企業と医療関係者が共に歩みを進められるような状態を作ることができれば、地域ビジネスプランニングは成功といえるでしょう。
小沢氏:地域の患者さんを中心に据えるならば、医療関係者、製薬企業の本部、MRさん、そしてMSLさんも、それぞれが同じゴールを目指す者同士。ただゴールに至る道が異なるだけなので、本来的には協力できる関係のはずです。
データプロバイダーとしては、地域分析データによって各部署・職種が本来の役割を果たせるようになり、結果として製薬企業の内部における連携や外部の医療関係者との連携が円滑に進むことを願っています。その連携のもと、地域ビジネスプランニングが実行に移され、地域医療の最適化へとつながっていくような未来を実現したいです。
【取材協力】
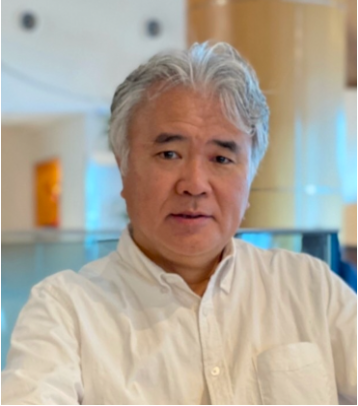
SalesTrainingLabo
代表
干潟 健夫 氏
グラクソ・スミスクライン株式会社、バイオジェン株式会社、アムジェン株式会社にて、コマーシャル部門の能力開発責任者として、多くのMRや営業マネージャー、営業部長、マーケティングスタッフなどのスキル育成やリーダーシップ開発、新組織立ち上げ、新製品発売準備に携わったのち、2024年3月より、SalesTrainingLabo を本格稼働。著書に「MR(医薬情報担当者)として成功したい君に問う十の質問」(2024年、ファストブック社)がある。

株式会社JMDC
製薬本部 マーケティングソリューション部 部長
小沢 晴久 氏
ジョンソン・エンド・ジョンソンなどを経て、医療系広告代理店マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパンに入社し、主に製薬会社・医療機器会社を担当。10年のアカウント経験ののち、2018年からGMとして5年間エージェンシーをリード。新薬ローンチ、リブランディング、デジタル戦略、インサイトドリブンマーケティングモデルの導入など、多くのプロジェクトを指揮。2023年7月JMDCに参画し、マーケティングソリューション部を新設。


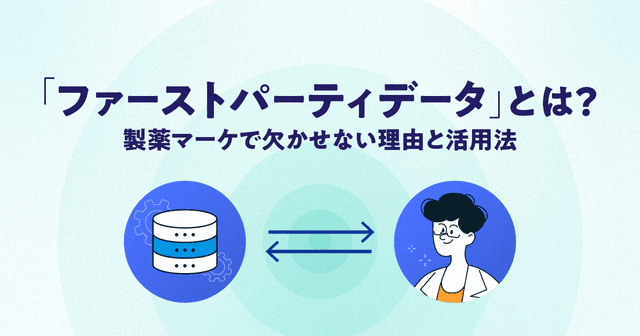








.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)



